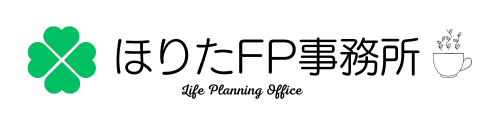投資信託の選び方|初心者が失敗しないためのポイント
少額から始められ、さまざまな資産に分散投資できる「投資信託(=ファンド)」は、投資初心者にも取り組みやすい資産運用のひとつです。
とはいえ、商品の種類が豊富でその違いはわかりにくく、「結局どれを選べばよいの?」と悩んで選ぶ手が止まってしまう人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、初心者が投資信託を選ぶときに知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
ご自身の資産形成に役立つファンド選びの参考になれば幸いです。
「投資信託」ってなに?
投資信託とは、多くの投資家から集めたお金をひとつにまとめて運用する金融商品です。集まった資金は、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに分散して投資します。投資信託をより広域にとらえて「ファンド」と呼ぶこともあります。
通常、個人で株式を購入するにはまとまった資金が必要ですし、複数の銘柄に分散しようとすればさらに多くの資金がかかります。一方で、投資信託であれば、1本購入するだけで、数百~数千社の企業の株式や、国内外の債券などに広く分散投資が可能です。
そのため、投資経験が浅い人や資金力が乏しい個人でも、比較的リスクを抑えながら投資を始めやすいのが特徴です。
ただし、価格の変動や為替リスクなどにより元本割れする可能性もあるため、あくまでも「投資」であることを理解し、仕組みやリスクを把握したうえで活用することが大切です。
投資信託の種類を知ろう|タイプ別に特徴を比較

投資信託にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると「投資対象(資産の種類)」と「運用方法」によって分類できます。
投資対象による分類(資産の種類)
投資信託は、投資対象(資産の種類)ごとに大きく4つのタイプに分けられます。
| 種類 | 特徴 |
| 株式型 | 株式に投資。値動きが大きく、リターンが期待できる反面、リスクも高め。 |
| 債券型 | 国債や社債などに投資。値動きは小さく、比較的安定した運用ができる。 |
| 不動産型(REIT) | オフィスビルや商業施設などの不動産に間接的に投資。株式や債券とは異なる動きをするため、分散効果が期待できる。 |
| バランス型 | 株式や債券など複数の資産に分散投資。リスクとリターンのバランスを取りたい人に向いている。 |
投資信託を選ぶうえで、まずは「どの資産を投資対象としているか?」の違いを理解することが大切です。
たとえば、ある程度のリスクをとりつつ、リターンを重視するなら株式型、安定性を求めるなら債券型を検討するといった投資手法がひとつの目安となります。迷った場合は、複数の資産に分散投資できるバランス型を選ぶのも選択肢のひとつです。
不動産型(REIT)は、他の資産とは異なる動きをするため、リスク分散の観点から組み合わせて活用するケースもあります。
各タイプの特徴を把握したうえで、自分のリスク許容度や投資目的に合ったタイプを選びましょう。
運用方針による分類
投資信託は、投資する「資産の種類」だけでなく「運用の方針」でも大きく2つに分けられます。それが「インデックスファンド」と「アクティブファンド」です。
| 種類 | 特徴 |
| インデックスファンド | 日経平均やS&P500など、市場の指数(インデックス)に連動するよう目指す運用手法。コストが低く、値動きがわかりやすい。 |
| アクティブファンド | ファンドマネージャーが銘柄を選定し、市場平均を上回る成果を目指す運用手法。高いリターンも期待できるが、手数料が高くなる傾向。 |
インデックスファンドは、「市場と同じ動きをすること」を目指す運用スタイルです。
たとえば「TOPIXに連動する」など、目指す基準が明確で、初心者にも選びやすいのが特徴。信託報酬などの運用コストも低く、長期保有に向いています。
一方のアクティブファンドは、市場平均を上回る成果を目指す積極運用型です。経験者や市場動向に興味がある人には向いていますが、初心者にはやや難易度が高い面もあります。
またアクティブファンドでは、投資先の銘柄を選ぶ判断や、買い時・売り時を見極める力などの「ファンドマネージャーの判断力」が運用成績に大きく影響します。運用がうまくいけば大きな利益が期待できますが、手数料が高くなることや成果が安定しないリスクも否めません。
初心者の方はまず「インデックスファンド」から検討し、資産運用に慣れてきたら「アクティブファンド」にも関心を広げてみる、というステップを踏むのがよいでしょう。
投資先の地域にも注目しよう|地域別の特徴とリスク
投資信託は、どの「地域」に投資しているかによっても性質が大きく異なります。大きく分けると「国内型」「海外型」「全世界型」の3つがあり、それぞれリターンやリスクの特性に違いがあります。
| 地域タイプ | 特徴 |
| 国内型 | 為替リスクがなく、値動きが比較的穏やか。日本経済に連動した運用が行われる。 |
| 海外型 | 為替や政治の影響を受けやすいが、高い経済成長が期待できる地域に投資できる。 |
| 全世界型 | 複数地域に分散投資でき、リスクを抑えつつ安定した運用を目指せる。 |
国内型|身近な投資先で安心感
日本国内の株式や債券などを中心に運用するタイプです。すべて円建てで取引されるため為替変動の影響を受けず、値動きも比較的安定しています。
経済情勢も身近に感じられ、情報収集もしやすいため、投資初心者にとって取り組みやすい選択肢です。
投資信託の一例:はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)、ニッセイ国内債券インデックスファンド など
海外型|リスクもあるが成長性に期待
アメリカやヨーロッパ、アジアなど国外の株式や債券に投資するタイプです。
為替変動や政治情勢といったリスクはありますが、高い成長が見込める国や地域に投資できるという大きなメリットがあります。
また、海外型には「先進国型」「新興国型」など、投資先をさらに細かく分けた商品もあるため、自分の投資目的に応じて選びましょう。
投資信託の一例:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
全世界型|1本で地域分散が完結
日本・先進国・新興国すべてを含む「全世界型」は、地域を問わず分散投資ができるタイプです。
特定の地域に偏らず運用できるため、景気変動の影響を受けにくく、長期投資向きの運用スタイルといえます。
「どこに投資すればいいか分からない」「リスクを抑えたい」という人にとって、安心感のある選択肢です。
投資信託の一例:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、楽天・全世界株式インデックス・ファンド
投資信託にかかる費用を確認しよう
投資信託を選ぶうえで、費用の確認はとても重要なポイントです。知らずに購入してしまうと、想定以上にコストがかかり、リターンが目減りしてしまうこともあります。
以下は、代表的な費用の種類とその特徴です。
| 費用項目 | かかるタイミング | 内容 |
| 購入時手数料 | 購入時 | ファンドの購入時にかかる手数料。 無料(ノーロード)〜3%程度まで幅がある。 |
| 信託報酬 | 保有中 | ファンドの運用・管理にかかる費用。年率0.1〜1.0%程度。 毎日少しずつ差し引かれるため、長期投資ほど影響が大きい。 |
| 信託財産留保額 | 解約時 | 解約時にかかることがあるコスト。 ファンド内の他の投資家に不利益が出ないようにするための調整費用の意味合いがある。 発生しない商品もある。 |
なかでも注目すべきは「信託報酬」
なかでも注目してほしい費用は「信託報酬」です。これは保有している期間ずっと差し引かれる費用で、毎年じわじわと運用成績に影響を与えます。
たとえば、年1%の信託報酬がかかるファンドを10年間保有した場合、単純計算でもトータルで10%相当のコストが発生することになります。
そのため、長期運用を前提にしている場合は、なるべく信託報酬が低いファンドを選ぶのが基本です。インデックス型のファンドには信託報酬が低い商品が多いため、コスト面からも選ぶ際の参考になります。
ファンド選びは「費用」だけで決まらない
投資信託にはさまざまな費用がかかることをご紹介しましたが、本当に自分に合ったファンドを選ぶためには、費用以外にも見るべきポイントがあります。
次のセクションでは、「投資信託を選ぶときのポイント」として、運用方針や実績、純資産総額など、初心者が特に注目したいチェック項目を解説します。
投資信託を選ぶための5つのステップ

投資信託の種類や費用を理解できたら、次は「どのファンドを選ぶか」という実践的なステップに入っていきましょう。
ここでは、初心者の方が失敗を避けながら自分に合った投資信託を選ぶための、5つのステップを紹介します。
ステップ1.投資の目的を明確にする
まず大切なのは「なぜ投資するのか?」という目的をはっきりさせることです。目的によって選ぶべきファンドの種類やリスクの取り方が変わってきます。
例
- 資産形成のために長期で積み立てたい
- 老後資金をじっくり育てたい
- 子どもの教育費のために10年以内に資金を用意したい
目的が明確になることで、投資期間やリスク許容度の目安も見えてきます。
ステップ2.リスク許容度を把握する
次に「自分がどの程度のリスクをとれるのか」を把握しましょう。リスク許容度とは、投資によって価格が上下したとき、どの程度まで精神的・経済的に耐えられるかをはかる目安です。
- 元本割れに強く不安を感じる → 債券型やバランス型を検討
- 値動きにある程度慣れている → 株式型やアクティブ型も視野に
リスク許容度は「一般社団法人全国銀行協会」の公式サイトで提供されている「リスク許容度診断」などのツールを使ってはかることができます。
簡単な質問に答えるだけでリスク許容度を把握できるため、ぜひ一度試してください。
ステップ3.ファンドの基本情報をチェックする
リスク許容度が分かったら、それに合う投資信託を探していきます。チェックすべき基本情報は以下のとおりです。
- 投資対象(株式・債券・不動産など)
- 投資地域(国内・海外(先進国・新興国など)・全世界)
- 運用スタイル(インデックス運用orアクティブ運用)
- 純資産総額(100億円以上が目安)
- 過去の運用実績(長期の成績が安定しているか)
純資産総額は「ファンドの規模」を表す指標のひとつとなり、100億円以上が目安です。規模が小さいファンドは資金力が乏しく、運用の途中でファンドが終わってしまう「繰上償還(くりあげしょうかん)」のリスクがあります。
予期せず運用終了になると、効率的な運用を妨げるおそれや、仮に含み損の状態で終了となった場合は損失を確定しなければならないリスクもあり、注意が必要です。
これらの情報は、各ファンドの「目論見書」や、金融機関の情報ページなどから確認できるため、購入前に必ずチェックしましょう。
ステップ4.低コストのファンドを選ぶ
同じような内容のファンドでも、手数料はそれぞれ異なります。とくに信託報酬は、長期で持つほど運用成績に大きな差を生む要素です。
比較するポイント
- 似たような運用方針のファンドは、信託報酬を比較する
- 購入時・解約時手数料はなるべく無料のものを選ぶ
- NISA口座を活用し、運用益を非課税にすることも視野に入れる
コストを抑えることで、運用効率が高まりやすくなることを意識しましょう。
ステップ5.長期保有できるかどうかを見極める
投資信託は価格の上下を繰り返しながらも、長期的な資産形成が期待できる商品です。そのため、10年以上を目安に長期間保有するのが基本とされています。
最後に、そのファンドが「自分にとって長く持ち続けられそうか?」という視点で確認しましょう。
注目ポイント
- 値動きが穏やかで、心理的に続けやすいか?
- 毎月の積立が生活に負担なく続けられそうか?
とくに初心者の方は、NISAのつみたて投資枠を活用し、毎月少額から積み立てていく方法がおすすめです。無理なく長期保有できるファンドを選ぶことで、コツコツと資産形成を続けやすくなるでしょう。
【投資信託の選び方】よくある質問Q&A
最後に、投資信託を選ぶ際に浮かびやすいギモンをQ&A形式でまとめました。
-
NISAで投資信託を選ぶときのポイントは?
-
信託報酬の低さと長期運用向きのファンドかどうかがカギです。
新しいNISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で購入できる商品が異なります。
とくに初心者には、金融庁の基準を満たした「長期・積立・分散」投資向けの商品がそろっているつみたて投資枠がおすすめです。なかでも、インデックス型のバランスファンドや信託報酬が低いファンドは、コスト面でも長期運用に向いています。
まずはつみたて投資枠から活用を始め、慣れてきたら成長投資枠の活用も検討するとよいでしょう。
-
初心者にアクティブファンドは向かない?
-
仕組みを理解したうえで選ぶならOKですが、まずはインデックス型から始めるのが安心です。
アクティブファンドは、市場平均を上回る運用成果を目指すぶん信託報酬が高めである点や、運用成績にばらつきがある点に注意が必要です。
初心者のうちは、値動きの大きさに不安を感じることもあるため、比較的コストが低く値動きもわかりやすいインデックスファンドから始めるのが安心です。
アクティブファンドに興味がある場合は、まずは少額から試してみるのが良いでしょう。
-
分配金あり・なし、どっちを選ぶべき?
-
長期投資には「分配金なし(再投資型)」が向いています。
分配金ありのファンドは定期的に利益を受け取れる一方で、元本が減ったり、複利効果が得にくくなるといった側面があります(特別分配金が含まれることもあります)。
一方、「分配金なし(再投資型)」のファンドは、得られた利益を自動で再投資に回すため、複利の力を活かした効率的な資産形成ができます。
なお、NISAのつみたて投資枠で購入できるファンドは、すべて「分配金なし(再投資型)」となっており、長期保有に適した構成です。
-
投資信託は毎月積立するべき?
-
長期運用を考えるなら、毎月積立が基本です。
毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」は、価格が高いときは少なく、価格が安いときは多く購入できるため、購入価格を平準化できる効果があります。
一括投資に比べて、価格変動リスクを抑えやすく、精神的にも安定して続けやすいのが特徴です。初心者にとっても、投資習慣をつける方法として有効な投資手法になるといえるでしょう。
まとめ:まずは少額から、自分に合うものを選ぼう
投資信託は種類が豊富で、選ぶ際に迷ってしまうかもしれませんが、「何のために投資するのか」「どのくらいリスクをとれるのか」という軸を持てば、自分に合った選び方が見えてきます。
選び方は人それぞれですが、
- 投資対象(資産や地域)
- 運用方針(インデックス型・アクティブ型)
- 手数料などのコスト
といった基本的なポイントは、どんな人にも共通してチェックすべき要素です。
投資信託は少額から始められる商品です。最初は毎月1,000円~5,000円程度の無理のない金額からでも構いません。まずは長期での運用を意識して始めてみるのがおすすめです。
「選び方」に悩んで手が止まってしまうよりも、まずは少額からスタートして、運用に慣れることが第一歩。経験を積むことで、自分なりの判断軸が自然と身についていくはずです。
長期的な視点を持ちながら、自分に合ったペースで取り組んでいきましょう。
※2025年7月時点の情報をもとに執筆しています。
※特定の金融商品を推奨するものではありません。